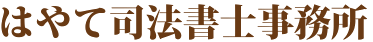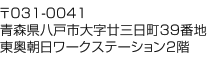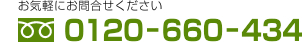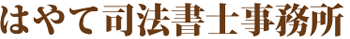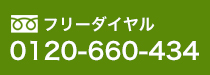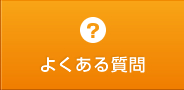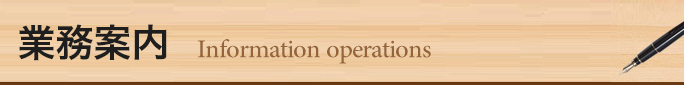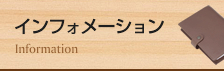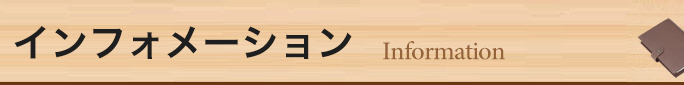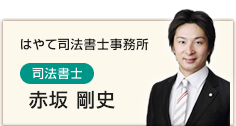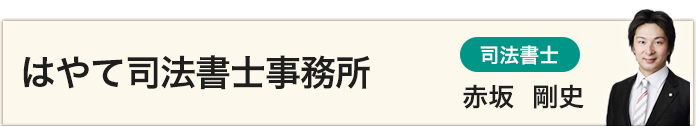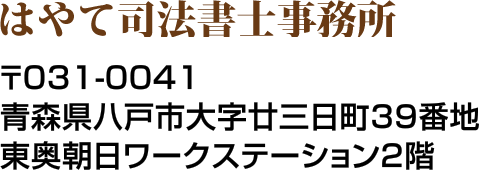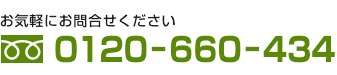・相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。なお、形式的に受理されても相続放棄の有効が確定するものではなく、法律上の無効原因などがある場合は、後でその有効性を訴訟で争うことも可能と解されています。
・3か月以内で判断がつかないときには、家庭裁判所に期間の伸長の申立てができます。
・相続開始後しばらくしてから債権者の請求を受け、そのときに初めて被相続人の債務の存在を知ったような場合には、相続開始後3か月を経過していても、相続放棄が認められる場合があります。
・相続放棄すると、その者は最初から相続人でなかったことになります。放棄者の直系卑属(子、孫など)について代襲相続が起きることもありません(第887条2項参照)。
・相続放棄により、法定相続における後順位の者が相続人となります。たとえば すべての子が相続放棄をすると、直系尊属(父母等)が相続人となります。さらに全ての直系尊属が相続放棄をすると、兄弟姉妹が相続人となります。また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
・相続財産が債務超過の場合、債務を免れるためには、これらの者全てが相続放棄をする必要があります。
・あくまでも、家庭裁判所に申し立てをし受理されることにより相続放棄が認められるのであり、一般的に「遺産はいらない」と口頭などで相続人に伝える「放棄」とは違います。
この場合には協議による「遺産分割」という扱いになります。
・なお、被相続人が死亡する前に相続を放棄することはできず(民法915(1))、生前にした相続を放棄するという契約も無効となります。